熟 年 離 婚・年 金 分 割 に つ い て
かすかべ総合離婚支援センター
熟年離婚と年金分割の関係性
夫と妻では、受給する年金額に大きな開きがあります。
現行制度においては、専業主婦をしていた妻は基礎年金だけしか受給できないのに対して、夫がサラリーマンだった場合、夫は基礎年金に加えて厚生年金から報酬比例の年金を上乗せして受給できます。
つまり、夫婦二人合わせた年金でその一世帯の生活体系となります。
しかし、離婚をするとこの仕組みが崩れ、妻は家庭生活を支えてきたにもかかわらず支給されるのは基礎年金だけです。対して、夫は基礎年金の他に報酬比例の年金を独り占めをするように(図表1参照)になっています。
離婚裁判での財産分与では、夫が年金支給前でも扶養的財産として妻に定期的に支払うものや婚姻期間に応じた両者の年金額の差額分を試算して、その半分を分与するために年金支給開始後からその金額を送るようになりました。
年金権は一身専属性のものであり、他の方にその権利を譲り渡した後で担保にしたり、また差し押さえの対象にすることができません。
その為、判例のように、元夫へ支給された年金から元妻に送金するという約束しかできません。
これらのことを踏まえ、平成16年の年金改正で年金分割制度が改善(図表2参照)されました。そのおかげで、年金の一身専属性を存続しながらも、判例のような欠点をカバーすることができるようになりました。
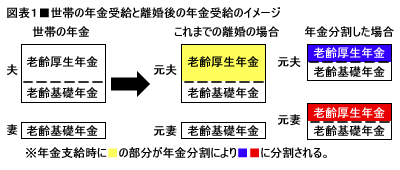
年金分割は2種類
図表2
| 合意による分割(任意分割) | 3号期間対応の分割(強制分割) | |
| 施行時期 | 2007年4月 | 2008年4月 |
| 対象期間 | 婚姻期間(事実婚の第3号被保険者期間)(2007年4月前の期間を含む) | 2008年4月以降の第3号被保険者期間に対応する期間 |
| 当事者の定義 |
|
|
| みなし期間 |
「離婚時みなし被保険者期間」 分割で新たに得た厚生年金被保険者期間で、第2号改定者の厚生年金被保険者期間であったとみなすもの |
「被扶養配偶者みなし被保険者期間」 分割で新たに得た厚生年金被保険者期間で、被扶養配偶者の厚生年金被保険者期間であったとみなすもの |
| 分割割合 | 按分割合の上限は双方の持ち分の合計の2分の1、下限は第2号改定者の持ち分 | 特定被保険者の持ち分の2分の1 |
| 分割手続き | 双方で按分割合に合意(または裁判所の決定等)のうえ、社会保険庁に標準報酬改定請求手続きをす | 合意不要で、第3号被保険者が社会保険庁に標準報酬改定請求手続きをする |
| 手続期限 | 離婚成立後原則2年(特例あり) | 離婚成立後いつでも |

第1号被保険者・・・20歳から60歳未満の自営業者、学生、無職の者
第2号被保険者・・・民間会社員、公務員で厚生年金、共済の加入者のことをいいます。
第3号被保険者・・・第2号被保険者の配偶者である専業主婦(主夫)の夫又は妻。
年金分割請求の手続きの仕方
合意による分割は、原則的に離婚成立後2年以内(裁判などの決定が遅れた場合に関しては、例外もあり)に、合意した公正証書(または裁判による決定書など)その他戸籍謄本等を送付して請求手続きをする必要があります。
離婚と同時に分割請求したい時は、離婚する前に事前の話し合いや合意書面の準備が必要です。なお、公正証書で作成する場合は、当事者が請求すべき按分割合(例えば50%)について合意したことや当事者の標準報酬の改定、又は決定の請求をすることが記載されていなければなりません。年金分割案を織り込んだ公正証書による離婚協議書作成は、埼玉県春日部市のよこやま行政書士事務所に是非お任せ下さい。
よこやま行政書士事務所
〒344‐0038
埼玉県春日部市大沼5丁目149番地6
電話 048-711-2801
埼玉県行政書士会春日部支部 所属
かすかべ車庫証明センター・ 春日部支部主催 無料相談会相談員
埼玉県行政書士会推薦出張封印(丁種)登録行政書士
文化庁登錄著作権相談員・埼玉県行政書士会 被災者支援相談員
こしがやii(あいあい)ネット加盟・「市民の相続を考える会」事務局

対応エリア
埼玉県
春日部市・越谷市・草加市・幸手市・川口市・吉川市・八潮市・久喜市・三郷市・加須市・羽生市・蓮田市・蕨市・上尾市・伊奈町・戸田市・杉戸町・宮代町・白岡市・松伏町・さいたま市(北区・西区・緑区・見沼区・浦和区・大宮区・岩槻区)
茨城県
五霞町・境町・坂東市
千葉県
野田市
