相続関係説明図・法定相続情報一覧図の達人
任せて安心、地域に密着した、信頼できるサービスの提供を。
1. 相続関係説明図とは?
相続関係説明図とは、被相続人(亡くなった方)とその相続人との続柄(親子関係、配偶者関係など)を図式化したものです。
戸籍の情報に基づいて作成され、誰が相続人に該当するのか、相続順位や人数などを明確にする役割があります。
何のために作るのか?
主に以下の手続きで提出が求められます。
-
銀行預金の相続手続き
-
不動産の名義変更(相続登記)
-
相続税の申告資料として
-
遺産分割協議書作成時の参考資料
法務局では相続登記の際に、戸籍の束の代わりに相続関係説明図を添付すれば戸籍の原本を返却してもらえるというメリットもあります。

2. 法定相続情報一覧図とは?
被相続人(亡くなられた方)の法定相続人が誰かを一覧化した図(表)であり、それを登記官(法務局)が認証したものを「法定相続情報一覧図の写し」として交付してもらえます。
これをもって、金融機関・税務署・証券会社・不動産登記など、さまざまな相続手続きに使い回すことができる非常に便利な制度です。
法定相続情報一覧図の特徴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行者 | 法務局(登記官) |
| 構成 | 被相続人・相続人の氏名・生年月日・死亡日・続柄を一覧で記載 |
| 効力 | 公的証明書として複数の機関に利用可能 |
| 有効期限 | 明確な期限なし(ただし新たな相続人が発覚した場合などは注意) |
| 利用場面 | 銀行口座解約、相続登記、証券口座、年金、保険、税務署など多数 |
制度のメリット
-
✅ 戸籍一式を何度も提出する手間が不要
-
✅ 各機関に「同じ証明書」を使い回せる(複数枚交付可能)
-
✅ 書類の整合性が法務局で確認済みであるため、信頼性が高い
3. 相続関係説明図(法定相続情報一覧図)のモデルケース「雛型」をご紹介
相続関係説明図を作成・添付した登記申請の場合は、原本還付を受けることができます。
原本還付とは、登記の完了後に申請に添付した戸籍謄本等の原本の返還を受けることです。
平成29年5月29日よりはじまった法定相続情報一覧図も、相続関係説明図と同様の記載内容をもつ書類です。ただ、こちらは法務局の証明がついたものなので、登記申請等の前に、予め法務局に法定相続情報一覧図の保管と交付の申し出を行う必要があります。
法務局より法定相続情報一覧図の交付を受けた場合は、各種の払い出し請求書や登記申請書にそれを添えることで、金融機関や不動産の名義変更を行う際に、戸籍謄本等の添付を省略できます。
よこやま行政書士事務所はこの法務局への申し出をお客さまに代わりまして(代理人として)行います。
下図は、先妻と死別し、その後再婚した場合の相続関係説明図(法定相続情報一覧図)の例です。
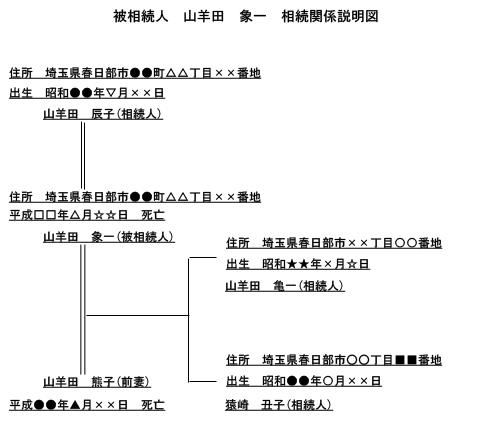

下図は、父親が死亡した時点で既に息子が死亡している場合の相続関係説明図(法定相続情報一覧図)です。 ※代襲相続のパターン


4. 相続関係説明図・法定相続情報一覧図を作成する時の必要書類
相続関係説明図・法定相続情報一覧図を書く時の必要書類は次の5つです。
- 亡くなった人の最後の住所を証する書面(住民票の除票もしくは戸籍の附票)
- 被相続人(亡くなった方)の除籍謄本
- 法定相続人が確定するまでの、連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍
- 相続人全員の住民票の除票もしくは戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本(亡くなった日以降の日付のもの)
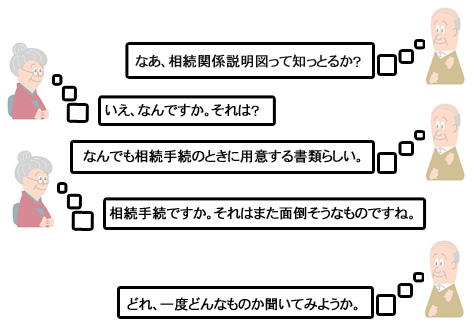
相続関係説明図・法定相続情報一覧図には、個々のご家族の特性及び相続人間の関係性を正確に反映させる必要がございます。
上記の相続関係説明図・法定相続情報一覧図の見本は、あくまでも一般的なものをベースとしておりますので、お客様のケースによっては、そのままお使いになれない場合もございます。
5. 相続関係説明図・法定相続情報一覧図に関するよくある質問(FAQ)
Q1. 相続関係説明図とは何ですか?
A. 相続関係説明図は、被相続人(亡くなられた方)と法定相続人の関係を示す家系図のような図です。相続手続き(不動産登記や銀行口座の名義変更など)に使用され、戸籍の内容を視覚的に表現することで相続人の関係性を明確にします。
Q2. 法定相続情報一覧図とは何ですか?
A. 法定相続情報一覧図は、戸籍の内容に基づき作成した相続人の一覧を、法務局が認証する公的書類です。これにより、複数の金融機関や役所などで相続手続きが効率化されます。戸籍一式の提出を省略できる大きなメリットがあります。
Q3. 両者の違いは何ですか?
A. 相続関係説明図は、形式自由で登記や手続き用の補助資料です。一方、法定相続情報一覧図は、法務局が内容を確認・認証した公的証明書で、使い回しが可能です。どちらも戸籍に基づいて作成しますが、一覧図は認証付きの信頼性が高い書類です。
Q4. どちらも作成が必要ですか?
A. ケースにより異なりますが、相続登記などでは相続関係説明図があれば十分な場合もあります。ただし、複数の機関に手続きする場合や、戸籍の束を何度も提出したくない場合には、法定相続情報一覧図の活用が推奨されます。
Q5. 作成にはどのような資料が必要ですか?
A. 主に以下の書類が必要です。
-
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
-
相続人全員の戸籍謄本・住民票
-
被相続人の住民票除票
-
必要に応じて遺言書や除籍簿等
収集には相当な手間と時間がかかることがあります。
Q6. 自分で作成することは可能ですか?
A. 可能ですが、戸籍の読み解きや相続関係の正確な整理が必要です。相続人が多い場合や代襲相続・養子縁組がある場合などは、専門家のサポートを受けた方が安心です。
Q7. 法定相続情報一覧図はどこで取得できますか?
A. 法務局(登記所)で申出を行います。申出人は、法定相続人のうち1人でも可能です。申出時には、相続関係を示す一覧図の原本や戸籍一式の原本を添付する必要があります。手数料は無料です。
Q8. 一覧図の写しは何部でももらえますか?
A. はい。法務局で「写し」を複数部発行してもらうことができます(申出時に希望枚数を記載)。金融機関ごとに提出できるため、非常に実用的です。
Q9. 間違った相続関係で作成するとどうなりますか?
A. 相続関係の誤り(相続人の漏れ、続柄の誤認など)があると、登記や口座解約が拒否されるほか、遺産分割の無効につながる可能性もあります。正確な戸籍収集と、法的知識に基づく作成が重要です。
Q10. 専門家に作成を依頼することはできますか?
A. もちろん可能です。よこやま行政書士事務所では、戸籍の収集から相続関係説明図・法定相続情報一覧図の作成・提出まで、すべて代行可能です。相続人が複雑な場合や、手続きをスムーズに進めたい方は、ぜひご相談ください。
相続関係説明図や法定相続情報一覧図の書き方、または戸籍の取得及び調査方法等のご不明な点は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
よこやま行政書士事務所
〒344‐0038
埼玉県春日部市大沼5丁目149番地6
電話 048-711-2801
埼玉県行政書士会春日部支部 所属
かすかべ車庫証明センター・ 春日部支部主催 無料相談会相談員
埼玉県行政書士会推薦出張封印(丁種)登録行政書士
文化庁登錄著作権相談員・埼玉県行政書士会 被災者支援相談員
こしがやii(あいあい)ネット加盟・「市民の相続を考える会」事務局

対応エリア
埼玉県
春日部市・越谷市・草加市・幸手市・川口市・吉川市・八潮市・久喜市・三郷市・加須市・羽生市・蓮田市・蕨市・上尾市・伊奈町・戸田市・杉戸町・宮代町・白岡市・松伏町・さいたま市(北区・西区・緑区・見沼区・浦和区・大宮区・岩槻区)
茨城県
五霞町・境町・坂東市
千葉県
野田市
